
熱がある

熱がある
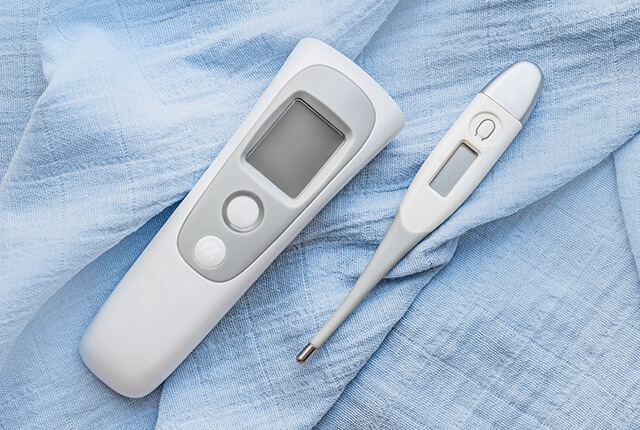
子どもは免疫が発達途中のため、大人よりも熱を出しやすく、発熱は細菌やウイルスとたたかうための大切な防御反応です。多くの場合は大きな心配はいりません。まずは水分補給と十分な休息を心がけてください。ご不安なときは、いつでも当院へ受診ください。
こどもの平熱は一般的に36.5〜37.5℃程度です。通常、37.5℃以上を発熱とします。
次のような場合には、すぐに受診をしてください。
元気があり、熱が一時的に下がっていれば短時間の入浴は可能です。ただし、ぐったりしているときや高熱が続く場合は控え、体をふいてあげる程度にしましょう。
もちろんです。特に赤ちゃんや発熱が初めてのお子さまの場合は、医師の診察を受けることで安心につながります。
概要
主にウイルスによる上気道感染で、多くは自然に軽快します。
症状
発熱、鼻水・鼻づまり、くしゃみ、咳、のどの痛み、食欲低下など(乳幼児は機嫌不良も)。
感染経路
咳やくしゃみの飛沫、鼻水や唾液が付いた手指・物品を介した接触で広がります。
診断
症状と診察で総合判断し、必要に応じてインフルエンザや新型コロナ等の迅速検査で鑑別します。
治療
水分・休養、解熱鎮痛薬や去痰薬などの対症療法が基本です。抗菌薬は原則不要で、細菌感染が疑われる場合に検討します。
登園・登校
出席停止の対象ではありません。発熱がなく全身状態が良ければ可能ですが、無理はせず休養を優先してください。
予防
手洗い、咳エチケット、換気・加湿、十分な睡眠と栄養。
概要
インフルエンザウイルスによって起こる感染症で、毎年冬を中心に流行します。風邪と似ていますが、突然の高熱や全身症状が強く出るのが特徴です。
症状
急な高熱(38〜40℃)、頭痛・筋肉痛・関節痛、全身のだるさ(倦怠感)、のどの痛み、咳、鼻水、胃腸症状(とくに子どもでは嘔吐や下痢もみられることがあります)
感染経路
飛沫感染(咳・くしゃみ)と接触感染(手やおもちゃなどを介して)でうつります。
診断
発熱後12時間程度で、鼻の奥の粘液をとって行う迅速検査キットで診断できます。
治療
抗インフルエンザ薬(タミフル、リレンザ、イナビル、ゾフルーザなど)、対症療法(解熱剤、水分補給、安静)
登園・登校
「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)」が経過するまで出席停止です。(発症日・解熱当日は0日目として計算)
予防
毎年秋にインフルエンザワクチンを接種すると、感染や重症化のリスクを下げられます。手洗い、うがいを行い、十分な睡眠と栄養をとりましょう。
概要
RSウイルスは、乳幼児に多い呼吸器の感染症を引き起こすウイルスです。特に1歳未満の赤ちゃんにとっては、重症化しやすく入院が必要になる感染症として知られています。
症状
発熱、鼻水・鼻づまり、咳、ゼーゼー・ヒューヒュー、呼吸が速くなる、苦しそうに見える、母乳・ミルクを飲まなくなる。
感染経路
飛沫感染(咳・くしゃみ)と接触感染(手やおもちゃなどを介して)でうつります。
診断
鼻水を少量とって迅速検査キットでRSウイルスの有無を調べます。
治療
RSウイルスには特効薬はありません。対症療法(症状をやわらげる治療)が中心です。
登園・登校
症状がなくなり、普段通りの生活ができるようになってからが基本です(熱が下がり、咳や呼吸状態が落ち着いたら)。
予防
手洗い・アルコール消毒、人混みを避ける、咳や鼻水がある人との接触を避けることが大切です。妊娠中にお母さんに接種するワクチン(アブリスボ)、ハイリスクな乳児(早産児など)には抗体製剤(シナジス、ベイフォータス)があります。
概要
新型コロナウイルスは、2020年以降世界的に流行した感染症の原因ウイルスです。主に呼吸器に症状を引き起こします。
症状
発熱、咳・のどの痛み、鼻水、倦怠感(だるさ)、頭痛、嘔吐・下痢(とくに乳幼児)、味覚・嗅覚異常(学童以降でみられることがあります)
感染経路
飛沫感染(咳・くしゃみ)と接触感染(手やおもちゃなどを介して)でうつります。
診断
抗原検査やPCR検査で診断します。
治療
こどもの多くは軽症で、自宅療養と対症療法で回復します。基礎疾患など重症化リスクがある場合は、適応に応じて抗ウイルス薬を検討します。
登園・登校
発症後5日が経過し、かつ症状が軽快した後1日経過していれば登園・登校可能です。(発症日を0日目と計算)ただし、発症後10日程度までは感染力が残る可能性があるため、周囲への配慮が必要です。
予防
手洗い・マスク・換気を基本としましょう。小児向けのコロナワクチンも対象年齢に応じて接種可能です。
概要
溶連菌(主にA群β溶連菌)は細菌の一種で、主にのどに感染して溶連菌咽頭炎(扁桃炎)を起こします。こどもに多く、5〜15歳が好発年齢です。
症状
のどの強い痛み、突然の高熱(38〜40℃)、いちご舌(舌の表面が赤くブツブツする)、のどの奥の赤みや白い膿(うみ)、首のリンパ節の腫れ痛み、腹痛、頭痛、吐き気(とくに小さな子ども)、発疹(「猩紅熱(しょうこうねつ)」と呼ばれます)
感染経路
飛沫感染(咳・くしゃみ)と接触感染(手やおもちゃなどを介して)でうつります。
診断
のどの粘液を綿棒でぬぐって、迅速検査キットで調べます。
治療
抗生物質(ペニシリン系など)をしっかり内服します。
登園・登校
抗生物質を飲み始めて24時間以上経過し、発熱などの症状が改善していれば可能です。
予防
手洗い・うがいをこまめに行う、タオルや食器を共有しないなど。
概要
ウイルス性の感染症です。耳の下にある「耳下腺(じかせん)」が腫れて痛くなるのが特徴で、子どもに多く見られます。
症状
発熱、耳の下(片側または両側)の腫れと痛み、ものをかむと痛い、食欲がない、だるい
感染経路
飛沫感染(咳・くしゃみ)と接触感染(手やおもちゃなどを介して)でうつります。
診断
問診と診察で診断します。
治療
特効薬はありません。症状を和らげる治療が中心になります。
登園・登校
発症後5日が経過し、かつ全身状態が良ければ可能です。
予防
ワクチンで予防が可能です。
概要
アデノウイルスによる感染症で、高熱、のどの痛み、目の充血が主な症状です。特に夏に流行することが多いです。
症状
急な高熱、のどの痛み、目の充血や目やに、頭痛、食欲不振、全身のだるさ、下痢
感染経路
飛沫感染(咳・くしゃみ)と接触感染(手やおもちゃなどを介して)でうつります。プールでも感染が広がることがあります。
診断
問診、診察、迅速検査で診断します。
治療
特効薬はありません。症状を和らげる治療が中心です。
登園・登校
熱や目の症状などの主要症状が治った“翌日”から2日間は自宅療養(出席停止)です。
予防
手洗い・うがいの徹底、タオルの共有を避ける、プールの後は目をよく洗い、シャワーを浴びる
概要
耳の奥(鼓膜の内側)にある「中耳」に炎症や感染が起こる病気で、乳幼児にとても多い疾患です。かぜをきっかけに起こることが多く、繰り返しかかるお子さまも珍しくありません。
症状
耳を痛がる、耳をさわる、発熱、夜にぐずる、機嫌が悪い、耳だれ、聞こえくそうにする
診断
耳鏡(鼓膜を見る器具)で鼓膜の腫れや赤み、膿の有無を観察して診断します。
治療
症状が軽い場合は経過観察します。症状が強ければ抗生剤を内服します。鼓膜の内部に液体が溜まる場合は、耳鼻咽喉科へ紹介します。
感染症以外にも、熱中症や自己免疫の異常、川崎病、白血病、腫瘍、甲状腺の病気などが原因で、発熱がみられることがあります。「熱がなかなか下がらない」「何度も熱をくり返す」といった場合には、他の症状がなくても、一度ご相談いただくことをおすすめします。
TOP